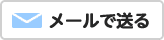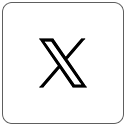小学館のマンガアプリ・マンガワンの10周年を記念したトークイベント「ウラバナシ」が、去る8月23日と24日の2日間、東京・小学館ビルで開催された。本記事では8月23日に行われた「『うしろの正面カムイさん』トークショー!」と「緊急会談!『ウラ漫』の未来!」の2つのトークイベントの模様をレポートしている。
“真面目”にお色気、「うしろの正面カムイさん」トークショー
「うしろの正面カムイさん」のトークショーには原作者のえろき、作画担当のコノシロしんこ、担当編集の成田卓哉氏が登壇。えろきはマンガワンの公式YouTubeチャンネルで公開されているドキュメンタリー番組「ウラ漫 ―漫画の裏側密着―」に登場した際のように、虫取り網を手に持ち、麦わら帽子にタンクトップ姿、そして顔面白塗りで現れ、客席をざわつかせる。その後、トーク中に白塗りのメイクを落としながら普段着に着替えたえろきは「『ウラ漫』を観てくださった方が来たときに、普通に出てきたらそれはそれでがっかりしてしまうかなと。以前の自分を超えろということで、アドオンしました」とファンサービス精神を明かした。
先日単行本の11巻が発売され、累計部数が100万部を突破した「うしろの正面カムイさん」。作品が始まったきっかけとして、えろきは「僕はどういうものが求められているのかオーダーを聞きたいタイプの作家なのですが、成田さんから『お色気とコメディがアツい』という言葉をいただいたので、そういう方向でやりましょうと。でもお色気もありつつ、バトルとか、もう1つの軸があるといいなと思い、もともと好きな領域だったのでホラー要素を入れることになって。お色気的な方法で除霊をする霊能力者を作ろう、というところから始まりました」と解説した。
読者から作中に出てくる妖怪に関しての質問が挙がると、えろきは「最初の頃はどれだけ連載が続けられるのかわからなかったので、面白そうなお色気なネタと、食い合わせがよいであろう妖怪をガンガン入れていって。連載が続けられそうだとわかってからは、切実な問題として、妖怪には数に限りがあると。なので、マイナーなものを挟み込みながら描いていくのを意識していくようになりました」と説明。またマンガワン内では掲載作品のおまけマンガやイラストを「ちょいたし」として公開している。「うしろの正面カムイさん」では、えろきのネームが完成したあとに「『ちょいたし』ではこういう絵がほしい」というリクエストが、コノシロのもとに送られるという。えろきとしては「いい意味で『こんなふうに言ってない!』という絵が上がってくることが多い」と称賛し、コノシロは「『ちょいたし』は(本編の)原稿が終わってすごく眠いときに、ガーッて気力で描いている感じはあります(笑)」と微笑んだ。
また読者からは、コノシロに対して「『カムイさん』は妖怪のときとかわいくなったときで、1キャラクターを実質2キャラクター分デザインしなければいけないが、作業量についてはどう思っているか?」という質問が飛び出す。コノシロは「えろき先生がネームの段階で怪異のキャラクターデザインをかなりしっかり決めてくださっているので、私のほうではデザインの作業自体は大変じゃないんです。どちらかと言うと、キャラクターを怖く描くのを苦戦している感じですかね」と回答。えろきは「女の子たちの服って僕だとわからないので『いい感じにしてください』と(ネーム)の横に書いていて。そこは本当に助かっています」とコノシロに感謝する。「僕が最初にシヅカのキャラデザを描いたときは、確か黒のハイソックスだったんです。それはたぶん、僕の世代が思う女子高生の靴下で。そうしたらコノシロ先生が『今はもう少し短いものなんですよ』と教えてくれて」とえろきが明かし、コノシロは「いつかは『なんだこの短さは、ダサい!』ってなるときが来るのかな(笑)」と想像した。
作中ではお色気ネタを扱っているものの、常に“真面目”に向き合っているというえろきとコノシロの2人。えろきは「僕はお色気ネタが好きな割に、そんなに描いたものがエッチにならないという弱点があって。もともと成人向けも描いていたんですが、『面白いけどあんまりエッチじゃない』とそのときから言われていて。なので『これくらいかな』と考えた(お色気要素が)ちょうどいい塩梅で面白い方向に寄ってくれている気はしています」と語る。読者から「作者の2人が変態すぎますが、どうしたらその高みに至れますか?」というコメントが寄せられると、えろきもコノシロは「僕らは真面目です」「仕事熱心なだけです。作品に向き合っていた結果がこれです」と自身をもって返答。しかし「でもそうですね……高み、高み……? 低みなのか?」と2人で首をひねらせた。
そのほかイベントではコノシロによるライブドローイングも実施。イベント中に描かれた色紙はじゃんけんで勝者となった読者にプレゼントされた。
人気コンテンツとなった裏側を振り返る、「ウラ漫」トークショー
「ウラ漫 ―漫画の裏側密着―」にスポットを当てたトークイベント「緊急会談!『ウラ漫』の未来!」には、番組にもたびたび登場しているマンガワン編集部の成田卓哉氏、千代田修平氏が登壇した。
2024年1月にマンガワンの公式YouTubeチャンネルでスタートした「ウラ漫 ―漫画の裏側密着―」。現在ではチャンネル登録者数が14万人を突破し、動画も人気コンテンツとなっている。千代田氏は「最初に企画の話が来たときは、編集者がもっと前に出ることによって生まれるメリットがいろいろとあると思ってやり始めて。それは作家さんに対してアプローチしていく手段として考えていたので、マンガ業界とは関係ないところでこんなに『ウラ漫』を楽しんでくださる方が増えるとは思っていなかった」と心境を述べる。成田氏は「最初は千代田くんが変なことを始めたなと思っていたんですけど(笑)、気づけばこんな規模になって。(マンガワン編集部への)持ち込みの数もすごく増えて。令和の新しい編集部の形の1つなのかなと思っています」と語った。千代田氏も「(小学館への)エントリーシートにも、半分以上に『ウラ漫を観て応募しました』と書いてあるらしい」と、その影響力の大きさを実感している様子だった。
作家や編集部との打ち合わせのほか、自身の部屋も動画内で公開していた千代田氏。撮影時には「渡邊D(演出・ディレクターを務める渡邊永人氏)に質問をされて、イラッとすることもけっこうあって。『なんでそんなことを聞くんだ?』と思うときもあったんですけど、蓋を開けてみると、渡邊Dの突っ込んだ姿勢が視聴者が知りたいものだったと思うので、そのグイッとくる姿勢があったから、『ウラ漫』が皆さんの期待に応えて伸びた1つの要因なのかなと思います」と振り返る。成田氏も「コメント欄を見ていても『編集の仕事を知らなかったけど、どういう仕事なのか、気になっていたところを明確に見せてくれている』という反響があるなと。確かに編集の仕事って意味がわからないですもんね(笑)。変な仕事だと思うけど、それが『ウラ漫』で具体化されたなと。『編集になりたい』という気持ちも、何をするのかわからないと湧かないですからね」と頷いた。
イベントでは「ウラ漫」のプロデューサーを務めるSync Creative Managementの行澤風人氏も登壇。「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」「THE ROLAND SHOW」など、さまざまな密着ドキュメンタリーを手がけてきた同社だが、行澤氏はもともとマンガワン作品も好んで読んでいたため、「ウラ漫」の企画の提案に至ったという。最初に企画書を受け取った千代田氏は自身でも「僕がめちゃくちゃ協力的だった」と振り返り、成田氏も「僕もそう思っていて、奇跡のマッチングだったなと。例えば僕とかが企画書を受け取っていたら『え? 大丈夫かな?』と思っていたかもしれない」と回顧する。行澤氏も「マンガ家さんも編集者さんも守るべきものがたくさんあると思うので、正直この企画が通る確率はどれくらいだろうと渡邊とも話しながら小学館さんに持っていったので、ここまで大きいコンテンツになるとは、企画をした側としても感じています」と言葉にした。
千代田氏の「動画の公開を始めた当初はどう感じていたか?」という問いに、行澤氏は「マンガ家さんと編集者さん、どちらにフォーカスを当てるのかを一番話し合っていた時期でした。物理的な話でいうと、やはりマンガ家さんが自分の仕事がある中で、YouTubeの撮影にずっと協力するのは難しいだろうなと。YouTubeという土俵で週に何本か動画を上げていく中では、編集者さんがメインになる体制のほうがいいかなと考えていました」と返答。「あと、個人的な気持ちとしてはマンガ家さんって“バケモン”で。そういう異常性や狂気性を期待して企画を立ち上げたところもあったんですけど、すべてを解明したくないという気持ちもあって。でも(視聴者が)観たいのはマンガ家さんというところもあると思うので、その橋渡し役として、編集者さんをメインにするのがいいんじゃないかと、配信しながら方向性ができていきました」と語った。
また企画が始まった当初、行澤氏は「1本目の動画としてティザー映像が公開されて、3~4時間経ったときに再生回数が2500回くらいだったんです。そうしたら千代田さんから『この数字をどう捉えてますか?』と、グループLINEに連絡が来て。千代田さんって言葉に重みがすごいので(笑)、LINEひとつでもどう答えるのが正解なんだろうなとお思いました」とエピソードを明かしながら「弊社ではYouTubeの事業をメインにやっていて、だいたい3カ月くらい経たないと何も見えてこないというのがあったので、そのときはそれを正直にそのまま伝えました。逆に言うと、その時期までは編集姿勢をブレずにやっていく」と説明。「(千代田氏の)あのメッセージが『再生数が低い』という意味だったのか、どうだったのか……」と疑問に思っている様子の行澤氏に、千代田氏は「僕はYouTubeを観ないので、本当にわからなかったんです。どれくらい再生されていると『回っている』と言えるものなのか、というのを理解してなかったので、本当にフラットに『うまくいっているのかな?』という意味で聞きました」と言い、行澤氏は「今ではそうだったんだろうなと思うんですけど、当時はまだそこまでの関係性もできていなかったので(笑)」と当時の様子を振り返った。また行澤氏は「自己分析になるんですけど、『ウラ漫』が伸びたのは、人間性だったりその人の背景だったりにフォーカスを当てているからなのかなと。千代田さんの家にもお邪魔もしましたし、いろんな方にプライベートな部分も話していただいて。それがどうなんだという話もありますが、“誰が作っているのか”というのをわかりやすくしたことで、マンガの内容や編集の仕事の内容がどんなものか入ってきやすいというのがあったのかなと思います」と想像した。
イベント内ではYouTubeのチャンネル登録者数が10万人を突破すると贈られる“銀の盾”の開封も行われた。今後の展望について、行澤氏は「新しい企画の構想も少しずつ考えています。始めて1年くらいは、ルール整備的なところも小学館さんとうちの中できちんと制定されていなくて。登録者数も伸びてきて、よさも悪さもあると思うんですけど、伸びたからには伸びた以上の、この段階での戦い方はしていかないといけないと思っています」と語る。千代田氏も「伸びてきてメジャー感を獲得したから、例えば有名な方とコラボするとか、そういった方面でもいろいろとやってみてほしいなと思います。一方で、初期の頃のインディーズ感を楽しんで観ていただいたとも思うので、その“尖り”みたいなものは維持していってもらえたらいいなと思っています」と話し、行澤氏も「僕らもその気持ちは持っています」と同調した。
イベントの後半、来場者に向けた質疑応答のコーナーでは多くの手が挙がり、読者はもちろん、編集者、マンガ家、就活生といったさまざまな立場から「ウラ漫」の動画の裏側やマンガ制作、編集者の仕事に関する質問が3人に投げかけられた。「ウラ漫」とマンガワン、それぞれの“今後の課題”についての質問に対し、行澤氏は「動画に出ていただくマンガ家さんや編集者さんは変わるんですが、密着取材先が同じなのと、そもそも動画に出れない方も多い。有り体に言うと、ネタが尽きていく部分もある。そんな中でも(マンガワン編集部から)たくさんアイデアもいただいて、僕らもアイデアを出しています。取材先が1つというのは変えられないものなので、もう一皮むけるためには……というのが、今の課題だと思っているところです」と模索している様子を明かした。
千代田氏は「マンガワンに多様な作品が載るようになって『マンガワンと言えばこういうマンガだよね』という、ブランドの方向性がわかりにくくなってきたなと思っていて。それをリブランディングするためにはどうすればいいんだろうと思っている」と語り、先日公開されたマンガワンの実写PVにも触れながら「僕はこれをめっちゃカッコいいと思っているんですけど。こういったものをやっている編集部はなかったと思う。載っている作品で差別化を図っていくのはここまでマンガ業界が巨大になった以上は難しいと思っているので、ほかの編集部はやってこなかった新しいことをやっている編集部なんだっていう、アプローチをやってみているけど、まだ十分とは思えていないので。どうやったらリブランディングできるんだろうと考えている」と回答。一方、成田氏は「ほかの編集部でやっていないことをやるというのもあるけど、ほかの編集部でやっていることをやれていないとも思っていて。アプリと紙の雑誌でマンガを読むのはそれぞれマンガ体験が違う。紙の雑誌のように、何かを読みに来たついでにほかの作品を(連載途中の話数から)楽しく読めたという経験がマンガワンではできないので、『この作品を読んでいたらこの作品も楽しめた』という見せ方ができることがあるといいなと考えています」と述べた。
(コミックナタリー)
 ERR_MNG
ERR_MNG